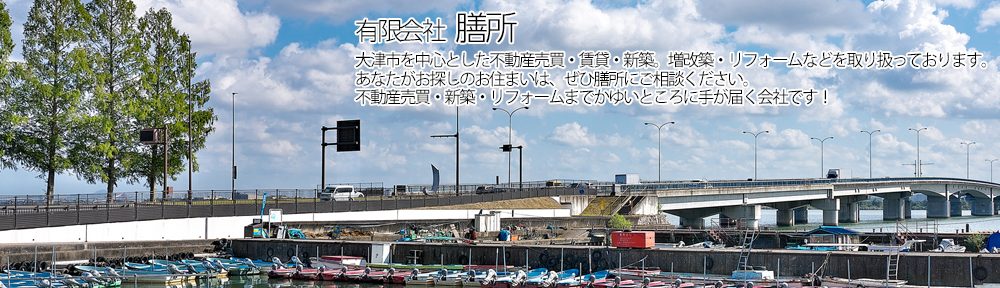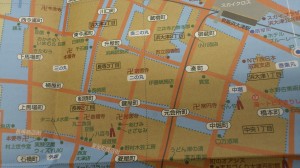弊社が所属いたしております公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会が主催する「堀尾正明氏 特別講演」が2013年1月20日(日)13時30分から15時00分に野洲市文化会館で開催されます。
堀尾正明氏は、元NHKアナウンサーで紅白歌合戦やオリンピック等の司会を担当され、現在は、フリーアナウンサーとしてテレビ・ラジオ等で活躍されています。
当日は、「地域活性化のために、何をすればいいか」~地域力取材活動より~という演題でご講演いただきます。先着800名様を無料ご招待させていただきますので、ご参加ご希望の方は、、フリーダイヤル0120-134-070までお気軽にお申し込みください!
※電話受付は、10時00分~12時00分・14時00分~17時00分(土・日曜日・祝日除く)